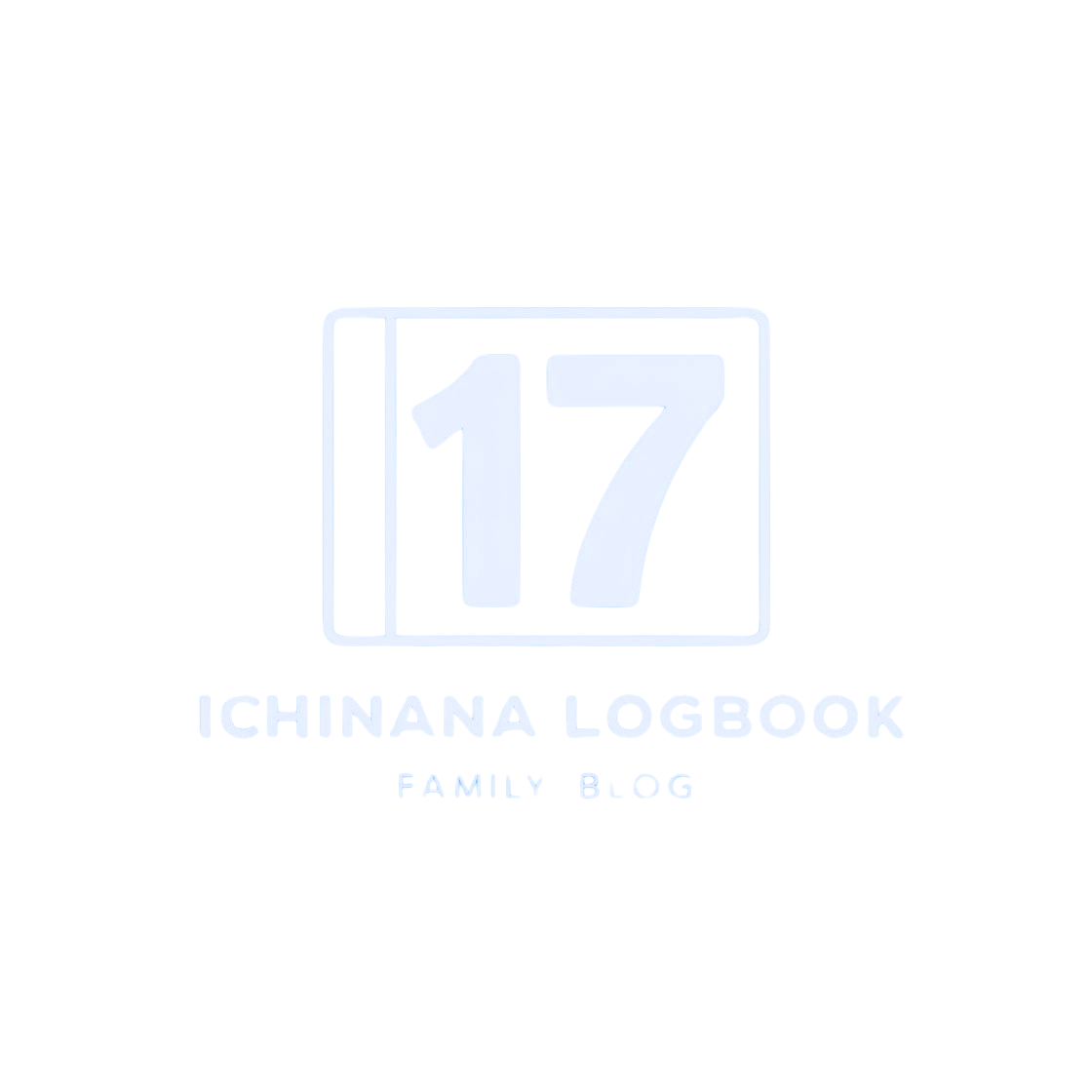冬の朝。リビングに差し込む柔らかな朝日と、湯気の立つ熱いお茶。静かに過ごしたい休日の朝に、突然…響き渡る声。
『かして!』
『ダメ!!』
『じゃあかさないよ!!』
『べつにいいよ!!!!』
今日も”兄弟喧嘩”が始まった。ワガ家の日常風景です。9歳長女と6歳次女による喧嘩のスタートです!
この記事の目次
目次
兄弟喧嘩への対応 パパのスタンス
二人の喧嘩は日常茶飯事。それもそのはず、力関係が拮抗しているので、どちらが泣いても不思議ではありません。そして泣いた方がパパのところに『パパー(泣)』とやってきます。
そしてパパが泣いた娘をなだめて、言い分を聞いて…『そうかー仲良くして欲しいな』と言って、これで終わりです。
パパはあえて“仲裁しない”
喧嘩は子ども同士で、解決する力を育てるチャンス!泣いた娘の言い分は正しいかもしれないし、片方の偏った言い分かもしれない。はたまたウソかもしれない。
たとえ一部始終を見ていても、パパがジャッジをすることはありません。パパは寄り添い役で十分です!過剰な暴力さえなければ間にも入りません。過剰な暴言くらいじゃ、微笑んで見守っています。
仲裁せずとも、子どもは自然と仲直りする

喧嘩が終わっても、パパが仲直りを提案したりなどすることはありません。再び娘たち2人で遊びたくなったら、仲直りすればいいし。気分が乗らなければプンプンしたまま別々に過ごせばいい。それで十分だと思っています。
放置していても、『さっきはごめんね』『これ一緒に使おう』と言って自然に仲直りしてます。親が介入せずとも、子供は成長します。
ただし、口を挟む場面が全くないわけではありません。
とはいえ…必要なタイミングでは“介入”も
長女の「ごめんね(怒)」に対して
長女が『ごめんね(怒)!誤ったから謝って』と言って、次女がこれを無視。
ここでパパの登場です!長女に諭します。『そんな気持ちのこもっていない謝罪だったらしない方がいい』感情に任せた謝罪では、相手には伝わりません。
謝罪の大切さを教えます。
次女のちゃちゃ入れから始まった兄弟喧嘩
つい先日も、次女が長女を小馬鹿にして喧嘩が勃発!ワタシは、まずいつも通り見守りです。そして、そのまま就寝の時間になり、みんなでベッドに入りました。
すると、長女が泣きながら
『ママに言うんでしょ(泣)?』
と言ってきたので、『言わないよ!だって2人は仲良しでしょ?』とワタシは返しました。そう伝えた後、ワタシは『ちょっとみんなで話そう!』と提案。
娘達3人で、話し合いの時間を持つことにしました。話し合いの中で、それぞれが自分の気持ちや行動を振り返ります。お互いに悪かったところを認めて謝れば、それで解決です。
子どもたちに「自分たちで解決する力」を育んでほしいと願いつつ、親としてのサポートは惜しみません。時にはパパだって頼れる相談相手になれるんです。
夫婦にも通じる|価値観は家庭ごとに違うもの
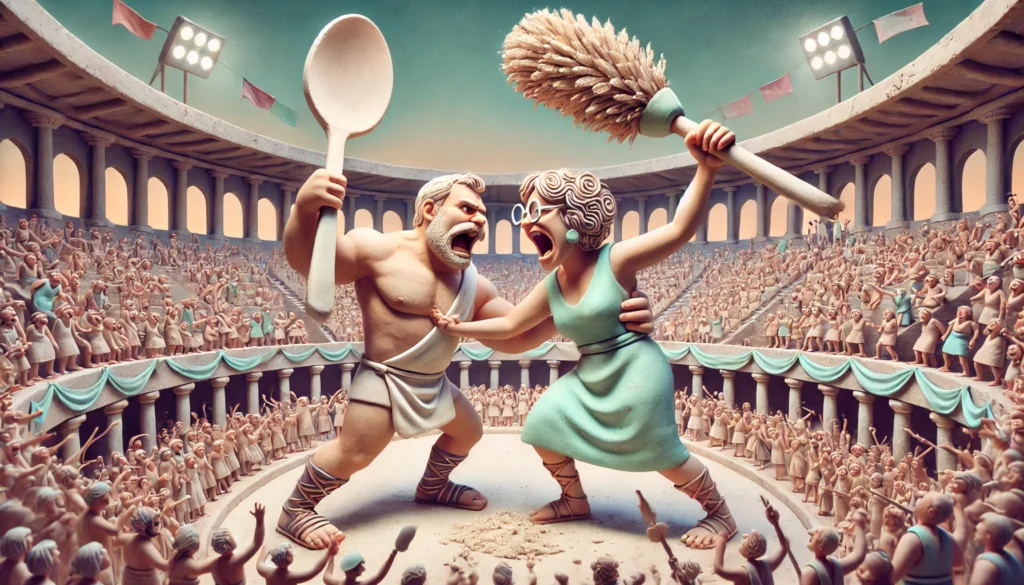
娘たちの喧嘩の話ですが、この考え方は夫婦関係にも通じると感じています。夫婦間で意見がぶつかった時に、第三者に仲裁を頼んだとしても、それは「一般的な正解」であって、必ずしも我が家に合うとは限りません。
夫婦それぞれが築いてきたルールは、外の価値観では測れないものです。夫婦はお互いに感謝や信頼し合ってなりたっている。たとえば、ワタシの適当過ぎる所や、無関心な所は、ワタシへの『感謝』『信頼』によって認められ、許されている。
とワタシは一方的に思っています。※妻に確認はとっておりません。
さいごに|兄弟喧嘩に必要なのは“仲裁”よりも“信頼”
娘たちの喧嘩を例にお話しましたが、子供も夫婦も『自分たちで築いていく関係』が大事だと思います。親として、パートナーとして余計な介入をせずに見守る姿勢が愛情の一つです。
自分でも驚きますが、ワタシは本当にテキトーです。妻にも多大な迷惑とストレスを与えていると思います。妻から言われた事はできる限り改善します。ですが全部を改善するとそれは、もはやワタシではありません。
「人それぞれ」「家庭それぞれ」でいいんです。今日も娘たちの兄弟喧嘩を背に、妻への感謝を胸に、にぎやかなワガ家を見守っていきます!
この記事のポイント!
- 兄弟喧嘩にパパは基本、仲裁しない
- 泣いた子の話は聞くがジャッジはしない
- 仲直りも子ども同士に任せる
- 必要なときだけ謝り方などで介入
- 話し合いで自分の気持ちを整理させる
- 親は“信じて見守る”姿勢が大事
- 兄弟喧嘩の対応は夫婦関係にも通じる
- 家庭のルールは家庭ごとでいい
こちらの記事もどうぞ!